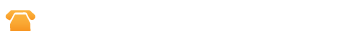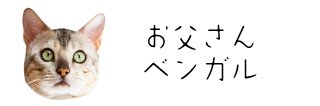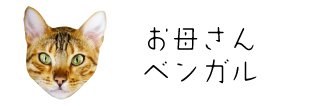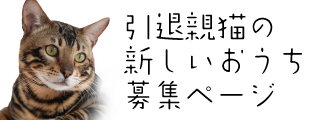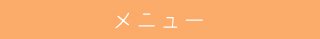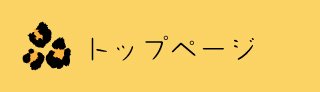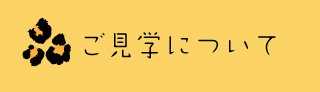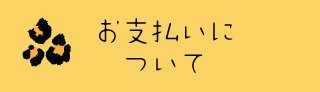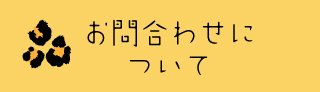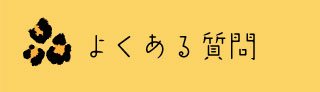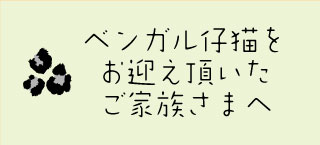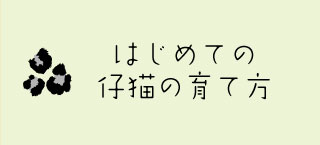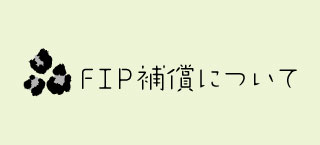ラパーマについて
Cattery夢猫庵ではベンガル猫の他に時々、ラパーマが産まれます。
ラパーマは、とても魅了的で独特な猫です。
普段はあまり鳴きませんのでおとなしく感じますが、賢く行動的で、とても人懐こく、犬のようについてまわったり、肩に乗ったり、掃除の手伝い(邪魔?)をしたり、テレビを見ている隣にそっと座ったりと、人の傍に一緒にいることが大好きです。
穏やかで愛情深い性質なので、子供や他のペットともうまく付き合うことができる反面、ひとりでお留守番する時間が長いと大変寂しがります。
ご家族様募集中のラパーマ子猫
ラパーマの特徴


ラパーマには巻き毛と直毛、短毛と長毛の仔猫が産まれます。
Cattery夢猫庵で生まれるラパーマの仔猫は、ネットで見かけるようなくるんくるんの巻き毛ではなく、ふんわりしたゆるふわカーリーの仔猫が多いです。
ジプシーシャグと呼ばれる、シャギーカーリーの柔らかい巻き毛は、まるでモヘアのようで、3種類のヘアタイプ(guard、awn、down)がすべて存在します。
彼らの巻き毛は、大きなカップ状の耳の内側にもあります。
巻き毛のラパーマは長毛と短毛、どちらのコートでもひげと眉毛はよじれています。
被毛の長さと充満度は、季節と猫の成熟度によって異なります。巻き毛で生まれた仔猫は成長とともに何度か(被毛の)脱落を繰り返しながら被毛が完成します。
夏には特に薄毛が目立ちます。
体型はミディアムロングまたはセミフォーリンの中型の猫で、やや細めのボディは筋肉質です。
オスは 8~10 ポンド(3.6~4.5㎏) 、メスは 6~8 ポンド(2.7~3.6㎏)です。
魅惑的な大きく表現力豊かなアーモンド形の目をしています。
ラパーマの歴史
1982年3月1日、Linda Koehl(リンダ・コール)は、Speedy(スピーディ)という名前のブラウンタビーの猫がサクランボ農園の納屋に6匹の子猫を抱えているのを見て、新しいrex突然変異の誕生を目撃しました。
その中の毛のない子猫は、体が長く細く、大きく幅の広い耳を持ち、タトゥーのように肌にはっきりしたタビーパターンがありました。
生後6週間でその子猫は、ブラウンクラッシックタビーの、まばらな縮れ毛のショートヘアの被毛になり、Lindaは彼女をCurly(カーリー)と名付けました。
Curlyは成熟するにつれて、柔らかい波状の被毛になりました。
繁殖の早い段階で、子猫の約90%が無毛で生まれ、その後3~4ヶ月でカーリーコートになりました。
ストレートの被毛で生まれた子猫たちの被毛は、ずっとまっすぐのままでした。
ラパーマは、2003年2月にTICAのチャンピオンシップの品種として認められました。
ラパーマの巻き毛


子猫は完全に発達したラパーマコートを持っていません。
これは特に長毛の子猫に目立ちます。
ラパーマの被毛は2歳以上になるまで発達し、完全に成熟するまでに2~3年かかります。
子猫は、頭のてっぺんのところから始まって、ほとんど完全にはげていきます。
このプロセス(脱毛)は、一般的に子猫が約2週齢になったときに始まり、彼らは最初の4ヶ月ほどの間にさまざまな段階の脱毛症になることがあります。
子猫は巻き毛で生まれた場合、脱毛しても被毛は一般的に戻ってきて、その後は常に巻き毛になります。
ラパーマは生涯にわたり、薄く散らばったような被毛を残す程度の脱毛から、フルコートまで変化します。避妊去勢後はフルコートになることが一般的です。
無毛で生まれた仔猫は、2~3年かけて成長とともに巻き毛が生え揃いますが、直毛で生まれた仔猫はほとんど一生涯、直毛のままです。
ごく稀に、直毛で生まれた仔猫が脱毛後に巻き毛になることがあるそうですが、ほとんどは直毛のままです。
ラパーマの巻き毛は、コーニッシュレックス、デボンレックス、セルカークレックスとは互換性がありません。(それぞれの巻き毛遺伝子は全く別の遺伝子です。)
ラパーマの血統書の名前の中にBB、BC、BSと記載されることがあります。
これは、 Born Bald(はげで生まれた)、 Born Curly (巻き毛で生まれた)、Born Straight(直毛で生まれた)という意味です。
ラパーマの育て方


ブラシよりもできれば櫛を使用して軽くコーミングし、デッドコートを取り除くことで、被毛を優れた状態に保ちます。
シャンプーのあとはタオルで、こすらず良く水分を拭き取ります。ドライヤーの使用は避けた方が良いです。
ラパーマは個体によって、薄毛の時期に皮脂が多く脂っこい肌になることがありますので、時々蒸しタオルで体を拭いてやります。
また、爪の付け根が皮脂で汚れたり、黒いタールのような耳垢がたまることがあります。そのため爪と耳の定期的な手入れが必要です。これは病気ではなく体質によるものです。
大変寒がりな個体が多いため、寒い時期は室温を高めに設定したり、ペットヒーターを設置する必要があります。